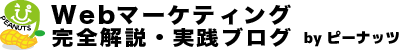SEOについて、正しく理解されている方は、思いの外少ないと感じております。
多くの方は、SEOの表面的な部分や、一部だけを見てSEOだと理解されているか、間違ったSEOやSEOを騙ったスパム的な手法をSEOであると認識されている方が多いです。
ちなみに、前回投稿した記事は挨拶のような記事で、コンテンツとしての価値は全くありませんでした。今回のエントリが実質的な第一回目のコンテンツの投稿となります。
今回のエントリでは、SEOとはなんなのか という点を解説していきたいと思います。
SEOと一言でいっても、人によって認識が異なります。
このエントリでは読者の皆様に同じ認識を持って頂けるよう、解説していきます。
SEOとはウェブサイトの内容や、そのコンテンツが持つ価値を検索エンジンに正しく伝える取り組み
「SEOってご存知ですか?」と尋ねると、「SEOってGoogle検索で1位に表示することでしょう?」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、それは結果であり、本質ではありません。
SEOとはSearch Engine Optimizationの略です。日本語に訳すと検索エンジン最適化となります。
検索エンジンに、ウェブサイトの内容や価値を、正しく伝える取り組みとなります。
Googleをはじめとした検索エンジンは、検索ユーザーが入力した検索クエリに対して、最も満足度が高いと考えられるページを上位表示させるという使命を持って動いています。
サイト管理者は、検索ユーザーが入力するであろう検索クエリに対して、検索ユーザーが満足する体験を、Webページを通して提供する必要があります。
検索ユーザーの疑問に対して的確なアンサーを持つ解説ページであったり、検索ユーザーの悩みの解決にドンピシャな商品販売ページであったり、ユニークな体験談であったりと、検索ユーザーが入力する(もしくは音声検索であったり)検索クエリの意図は様々ですが、検索者に対して優れた検索体験を提供することがSEOだと考えて頂ければわかりやすいかと思います。
検索エンジンの仕組み
検索エンジンの仕組みは簡単に説明すると下記の流れとなります。
- クローリング(Crawling)
クローラー(Crawler)(いわゆるGoogleボット等)がコンテンツを発見し、Webページの情報を収集します。 - インデキシング(Indexing)
クローラーが集めてきた情報を、インデクサー(Indexer)がページの内容を解析し、検索エンジンが使いやすいデータを生成してデータベースに登録します。 - スコアリング(Scoring)
検索ユーザーが検索クエリを送信すると、サーチャー(Searcher)は、データベースから検索クエリに対する答えとなる情報を取り出し、それぞれのページに検索エンジンが持つアルゴリズムに則ってスコアをつけ、最も検索意図に合致すると思われるページを検索結果画面に並べます。
Webページをクローラーが発見し、インデクサーにそのページの内容やHTMLタグ等の様々な要素を使いやすい形に変換したものがデータベースに登録され、サーチャーによってスコア順に並べられたものが検索結果(SERPs)です。
検索エンジンが行っている、クローリング、インデキシング、スコアリングといった働きに対して、様々な切り口からアプローチして、最適化していく作業も、SEOの実務の一部となっています。
3種類のSEO
ひとことでSEOといっても、そのアプローチ方法はいくつかにわかれます。
大まかに分類すると、下記の3つのSEOに分類されます。
なお、テクニカルSEOとコンテンツSEOは、自分のサイトに施す施策のため、オンページSEOに分類されます。
自サイトに施す最適化ではありますが、アプローチが全く異なるため、項目を分けて解説いたします。
マイナスを0に近づける、テクニカルSEO
自サイトのHTMLタグや、サイト構成、内部リンク構成を最適化させる取り組みをテクニカルSEOといいます。
内部SEOや、内的SEOとも呼ばれています。
- HTMLマークアップの最適化
- サイト構造の最適化
- リンク構造の最適化
- URLの正規化
- インデックス制御
- UIの調整
- UXの改善
それぞれの詳細は、今後、記事として公開予定しております。
主にソースコードを修正、調整する作業となります。
ソースコードに誤りがあったり、重要なHTMLタグがマークアップされていないといった理由で、サイトの内容が検索エンジンに正しく伝わっていない状況を改善させるための施策となります。
また、低品質なページを大量に保有している、ページの表示速度が遅い、セキュリティに問題がある、そもそもサイトが使いにくいといった、運用の問題を修正する作業も含まれます。
優れた情報が掲載されていたり、優れたユーザー体験が提供されているのに、構築で減点されていては、正しい評価が受けられません。
マイナス評価を極力0に近づける作業となります。
テクニカルSEOは-20点を0点にすることはできても、0点を10点にすることはできません。
いくら上手にマークアップ等を工夫しても、そのWebサイトやWebページが持つ情報の価値とは無関係だからです。
ソースコードの不備等の減点を極力減らす施策や、UX(ユーザーエクスペリエンス)が高い使いやすいWebサイトを構築する作業がテクニカルSEOです。
HTMLマークアップの最適化
HTMLタグをW3C勧告に準拠させてミスのないHTMLを書く といったイメージで捉えられる方もいらっしゃいますが、文法的な意味合いではなく、ページ構造をシンプルかつ、わかりやすく整理し、人間が理解しやすいようにHTMLマークアップを施す作業となります。
人間がわかりやすいページは、検索エンジンにとってもわかりやすいページになります。
また、タイトル要素やmeta要素を調整することにより、ページが取り扱っているトピックの内容を、検索エンジンやユーザーにわかりやすく伝えることも、重要な最適化作業です。
サイト構造の最適化
通常、Webサイトは、複数のページを組み合わせて構成されています。
それらのページはトップページからハイパーリンクでつながっているかと思います。
その際、特にサイト構造の設計を行わずにハイパーリンクでつなげるよりも、それぞれのページを分類し、整理し、つなげる方が効果的です。それらの構造の最適化を行います。
リンク構造の最適化
最適化されたサイト構造を検索エンジンに伝える際のヒントとして、リンク構造も利用されます。
SEOにおけるサイト構造の正体とは、リンク構造といっても過言ではないほど、綿密に関わってきます。
サイト全体のリンク構造を調整する作業も、テクニカルSEOの一部です。
また、関連記事へのリンクを張ることも、元ページのトピックや、リンク先のページのトピックを検索エンジンに伝える手助けとなります。
テクニカルSEOの重要度は年々下がってきている
検索エンジンは常に進化してきています。
HTMLタグのマークアップを極限までチューンしなくても、多くの場合でサイトの内容は検索エンジンに正しく伝わります。
また、一般的に使用されているCMSやショッピングカート(WordPressやShopify等)を適切に使用していれば、テクニカルSEOでチューニングする必要性は、少なくなってきています。
ただし、UXの優れたサイトを制作する必要は非常に高まっている
検索エンジンは昔に比べ、大幅に進化しました。
現在の検索エンジンはUX(ユーザーエクスペリエンス)(ユーザー体験)までスコアリングすることが可能となっています。
現在のテクニカルSEOで重要な施策は、マークアップの調整よりも、ユーザー体験の最適化をメインとすべきです。
テクニカルSEOは、一度施せば、以降はそれほど手間は掛からない
テクニカルSEOは一度行えば、日々の業務でしょっちゅういじくり回す といったことは殆どありません。
タイトル要素の調整や、新たに公開記事に対しての内部リンクの調整(こちらはシステム側である程度自動でつなげることも可能ですが)といったメンテナンスを行うことはありますが、基本的にHTMLタグは一度最適化してしまえば、触る必要はめったにないはずです。
一度最適化してしまえば、次からは触る必要がないテクニカルSEOのことを、初期SEOとよぶことがあります。
新規サイト構築やサイトリニューアルの際に、最初に施すものとなります。
今後の運用を考えると、コスパの良い施策となりますので、初期SEOの施策は一考の価値があるといえるでしょう。
ページやサイトの評価 100点満点を目指す取り組みがコンテンツSEO
自サイトに優れたコンテンツを積み重ねていって、サイトの持つ価値を高めていく取り組みがコンテンツSEOです。
自サイトに施すSEOという意味で、大きなくくりでは内部SEOや内的SEOと呼ばれるものの一部です。
一般的にソースコードやHTMLマークアップの調整といったテクニカルSEOのことを内部SEO(内的SEO)と呼ばれる事が多いので、それらと区別するためにコンテンツSEOとしています。
減点をいかに減らすかという取り組みが、テクニカルSEOならば、いかに加点を狙っていくかという取り組みがコンテンツSEOになります。
価値のあるコンテンツを公開する取り組み
考えてみてください。優れたWebサイトってどんなサイトでしょう。
2024年のSEOでは、一般的なWebサイトと、ECサイトでは、取るべきアプローチが大幅に異なってきますので、分けて考えてみました。
(一般的なWebサイトのベストプラクティスは、ECサイトでは全く使えなかったり、その逆も然りです)
優れたWebサイト
- 優れた情報が掲載されている
- 情報がふんだんに掲載されている
- 興味深い考察が掲載されている
- プロ目線の参考になるHow To記事が掲載されている
- ユーザー目線の生の声が忌憚なく掲載されている
優れたECサイト
- 求めている商品や、その代替品が取り揃えられている
- 興味のある商品のサイズ、色、スペック等
- 様々な数の商品が取り揃えられている
- 参考になるカスタマーレビューが多数、投稿されている
- その商品のメリット、デメリットもよく分かる
- 使いやすいサイト
品質の低いWebサイト
- 役に立つ情報が掲載されていない
- そもそもコンテンツが全く掲載されていない
- 自画自賛の技術力や商品の自慢ページしかない
- メリットばかりを並べた参考にならないセリングページ
品質の低いECサイト
- 求めている商品や、その代替品が取り揃えられている
- 興味のある商品のサイズ、色、スペック等
- 商品が取り揃い数が少ない
- でっちあげのお客様の声しかなく、商品を選ぶ参考にならない
- その商品のメリットは大々的に宣伝し、デメリットは隠す
- 使いにくいサイト
思いついた点をざっと挙げてみました。
皆さんそれぞれ、優れたサイトと品質の低いサイトのものさしは違うでしょうが、良いページは良い。悪いページは悪いという認識で間違いないはずです。
サイトの評価を高めるにはコンテンツが必要
コンテンツSEOとは、検索ユーザーの検索意図を満たす優れたコンテンツを作成し、公開していく取り組みのことをいいます。
コンテンツSEOは、2024年現在のSEOの主流となっている手法です。というか、テクニカルSEOをいくら頑張っても、コンテンツSEOを成功させない限り、SEOがうまくいく可能性は極めて低いといえるほど、重要な作業となります。
具体的にいうと、検索ユーザーの疑問に対してのアンサーとなるコンテンツのことです。
検索ユーザーがどのような悩みを抱えているのか。それらを解決するにはどうしたら良いのか。
余すことなく作り込んでいきましょう。
様々なアプローチでコンテンツSEOを成功させましょう
コンテンツSEOには様々な方法が存在します。
今後、当ブログで様々な方法を解説していきますので、参考にしてください。
第三者からの評価を獲得する、オフページSEO
オフページSEOとは、外部からの評価を獲得する施策となります。
外部からの評価は非常に重要です。
検索エンジンはサイトの出来やコンテンツの品質といった内的な評価以外に、外部から獲得している評価も検索ランキングを決めるアルゴリズムに組み込んでいます。
例えば、自サイト内で、「我が社の製品は世界一素晴らしい」と謳っところで、それは、なんの根拠もない自画自賛でしかありません。
第三者が、「株式会社〇〇の製品は品質が非常に高く、価格もリーズナブルであり、コストパフォーマンスを考えるとベストな選択である」といった記事なり、口コミを投稿することにより、そのサイトやそのページの信頼性が増します。そのため、サイトの人気を測る指標として、リンクや言及、口コミといった第三者の行動をランキングのアルゴリズムに組み込んでいるのです。
- サイトやブログ、SNS等からの被リンク(バックリンク)の獲得
- サイトやブログ、SNS等からの言及(サイテーション)の獲得
- 口コミ(カスタマーレビュー)の獲得
外部SEOや、外的SEOとも呼ばれています。
外部のサイトや、一般の顧客に、リンクや言及、口コミの投稿といった行動を行ってもらうための施策となります。
オンページSEOは自サイトに施す最適化のため、自身の権限で施策内容を自由にコントロール可能ですが、外部からの評価獲得が目的となるオフページSEOは、完全にコントロールすることは不可能です。
例えば、オンページSEOの内部リンクの最適化でしたら、自身でリンク構造を設計し、自由に最適化していくことができますが、被リンクにせよ、サイテーションにせよ、口コミの獲得にせよ、第三者が自発的に行う必要があります。
紹介記事を書いてもらって、リンクしてもらえるよう依頼することは可能ですが、実際にリンクするかどうかは第三者の胸三寸で決まります。
第三者が行動して初めて成り立ちますので、当然、第三者が自発的に行動するような優れたコンテンツであったり、優れたサービスが必要不可欠となります。
先ほど解説しました、コンテンツSEOは、自社で取り込むことが可能なオンページSEOですが、コンテンツをフックとし、被リンクや言及を獲得するオフページSEOの一面も持っています。
オフページSEOの手法
- ソーシャルメディア最適化(SMO)
- リンク依頼
- 口コミ依頼
- コンテンツSEO
- ローカルSEO
- 寄稿
- プレスリリース記事の配信
- マスコミへの情報提供
様々な方法で評価を獲得していきます。
それぞれの手法については、いずれ記事を作成予定です。
オフページSEOとは、広報活動と考えていただくと、わかりやすいかと思います。
いくら広報を頑張っても、中身が伴わなければ、誰も評判にしてくれない点も、リアルの広報活動と同じだといえます。
テクニカルSEO、コンテンツSEO、オフページSEOを組み合わせて、サイトの評価を高めましょう
今回のエントリで説明した、3つのSEO(テクニカルSEO、コンテンツSEO、オフページSEO)を組み合わせてサイト評価を高めていく取り組みSEOです。
もちろん、それら全てを完璧に施すことが出来るほどのリソースを持っている企業は少ないかと思います。
優先順位を決め、最適化してくことになるでしょう。
当ブログでは皆様の最適化作業の手助けになる記事をどんどん投稿していきます。
それらの記事も参考にして、やるべきSEOとやらないSEO、今は一旦保留のSEOの最適化作業の仕分けを行って頂ければ幸いです。